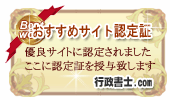各種書類に関すること
契約書の作成

私たちを取り巻く社会環境も日々変化し、それに伴い、各種契約をめぐるトラブルも増加しています。
かつて日本は信用社会で成り立っていましたが、現在は欧米化とともに契約社会へと変貌を遂げようとしています。
トラブルを回避するためには、どのような内容の契約書を作成するかが重要なポイントとなってきます。
契約書を作成するには、関係法令を踏まえたうえで約束した事項をきちんと網羅することも大事ですが、その契約にとって一番押さえたいことを明確に表現し、 重要な事柄は外さずに優先順位をつけていくことも重要です。
当事務所では各種契約書の作成や、発生したトラブルについて協議が整 っている場合には示談書・合意書等の作成を通じて、ご依頼者様の権利の保護、後々の紛争予防のサポートをいたします。
【契約とは】
当事者双方の意思の合致、すなわち合意があれば口頭であれ書面であれ契約として成立します。
ただし、契約書を作成せずに口頭のみで契約すると、契約内容が明確でなく解釈に食い違いが生じる、契約成立の証拠が残らないなどの大きな欠点が生じます。
また契約書を作成している場合でも、文章のちょっとした言い回し等により、その意図する効果が変わってしまう場合もあるため、うっかりすると不利になったり、役に立たない契約書になってしまう可能性もあります。
【契約書を作る際の注意点】
契約書を作成する場合には曖昧な表現は避け、誰が誰に対してどんな権利を持ち、又はどんな義務を負うかといった権利義務の主体を明確にすることが重要です。
そして、作成した契約書が印紙税法で定められた「課税文書」に該当する場合には、収入印紙の貼付が必要となります。
※作成した契約書が「課税文書」に該当するかどうかは、契約書の名称や呼称から形式的に判断するのではなく、契約書に記載されている内容に基づいて判断することになります。
課税文書に該当するかどうかは、国税庁が公開している「印紙税額一覧表」等から概ね判断はできるかと思いますが、それでも判断に迷うときは、管轄税務署に作成した契約書を持参して判断してもらうのが確実です。
契約書には署名もしくは記名押印が必要です。署名とは、本人が自分で氏名を書くことであり、記名とは署名以外の方法(PCで入力・ゴム印等)で自分の名前を記すことを指します。
記名したものに押印することで署名と同じ効力を持ちますが、証拠力という点では署名し、更に押印する事が望ましいでしょう。
押印は、本人が押印したか否かが重要です。認印と実印では効力は同じですが、実印の方が本人が押印した可能性が高いと判断されます。
【契約書の種類】
金銭の貸し借り(金銭消費貸借契約書)・ 土地、建物、動産の賃貸(賃貸契約書)・ 土地、建物、動産の売買(売買契約書)・ その他(贈与契約書、委託契約書、請負契約書、保証契約書、示談書 など)
公正証書の作成

『公正証書 (こうせいしょうしょ)』とは、公証人が権利義務に
関する事実について作成した証書です。
元裁判官などの法律のプロである公証人が作成することに
より、内容的にも安全な書面を作ることができ、強い証明力
をもたせることができます。
また、公正証書は、強制執行文言付きで作成することにより、
金銭債務を履行しない相手方に対して、裁判をすることなく強制執行をすることができます。
なお、公正証書の原本は公証役場で厳重に(原則20年間)保存されますので、紛失・盗難・偽造等を防ぐことができ、極めて安全です。
内容証明郵便の作成
トラブルが発生した場合に、自分の強い意志や要求を内容証明によって相手方に伝えることにより、法的手続きを取ることなく問題の早期解決を図ることができる場合があります。
【内容証明について】
自分の身の回りに起こったトラブルを早期に解決する手段として、相手方に自分の意思や要求を記した内容証明を送るという方法があります。
内容証明とは、郵便局が文面の内容を確認し、その文面が誰にいつ送られたのかを証明してくれるものであり、かつ、送付した文面と同様のものを郵便局に保管することにより、今後の紛争に発展した場合の証拠となり得るものです。
内容証明郵便には一定の規則があり、それに則ったものでなければありません。また、内容証明郵便を取り扱う郵便局も限定されております。
内容証明郵便を出すときは、窓口で配達証明付きにしてもらいます。それにより、その内容証明郵便が受取人に配達されたかどうか、更に、いつ配達されたのかを証明してもらうことができます。
【主な活用例】
慰謝料の請求 ・ 損害賠償の請求 ・ 売掛金の請求 ・ 貸金の返還請求 ・ 敷金の返還請求 ・ 婚約破棄 ・ 人事労務 ・ 家賃の不払い ・ 賃金の不払い ・ 近隣トラブル など
 みなとこうべ行政書士いとう総合事務所
Minato-Kobe Gyoseishoshi Lawyer office Ito
遺言、相続、成年後見など、ご家庭の法務に関する
お困りごとを、誠心誠意サポートいたします
お気軽にご相談ください
みなとこうべ行政書士いとう総合事務所
Minato-Kobe Gyoseishoshi Lawyer office Ito
遺言、相続、成年後見など、ご家庭の法務に関する
お困りごとを、誠心誠意サポートいたします
お気軽にご相談ください