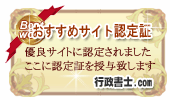相続
相続開始後の手続き

相続が開始すると、葬儀の準備や関係各所への届け出、その他細々とした手続きなど、しなければならないことが山のように押し寄せてきます。
それらの手続きを大きく分類すると、下記の2種類に分類することができます。
①「相続手続き」
(故人名義の財産を相続人の名義に変える手続き)
● 遺言書の検認(公正証書遺言以外の遺言があった場合)
● 相続人・相続財産の調査、確定
● 遺産分割協議、協議書の作成
● 不動産・預貯金等の名義変更 など
②「死後事務手続き」
(市区町村役場や税務署、年金事務所などへの届出が主なもので、相続手続き以外のもの)
● 死体火葬許可申請
● 世帯主変更届
● 生命保険金の請求 (注1)
● 未支給年金、国民年金の死亡一時金請求 など
(注1)
生命保険金については、受取人が誰になっているかによって扱いが変わります。
①特定の相続人が受取人になっている場合 ・・・ 保険金を受け取る権利は、その相続人の固有の権利であり、民法上の相続財産には含まれません。
(したがって、相続を放棄しても保険金を受け取ることができます)
ただし、税法上は課税対象となります。
②故人自身が受取人になっている場合 ・・・ 滅多にないケースですが、死亡保険金は相続財産となり、遺産分割協議の対象となります。
(したがって、相続を放棄した人は承継することができません)
相続手続きの流れと期限
● <被相続人の死亡 (相続開始)>
・ 通夜、葬儀の準備
↓
遺言書の有無の確認
相続人の調査、確定
相続財産の調査、確定
↓
● <7日以内> 死亡届の提出
・ 死亡診断書とともに市区町村役場に提出。
・ 火葬許可申請も同時に行う → 火葬後、埋葬許可証になる。
↓
● <3ヶ月以内> 相続放棄 ・ 限定承認 (マイナスの財産の方が多いときなど)
・ 故人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出。(相続開始を知った日から3ヶ月以内)
※ ただし、調査に時間がかかるなどの事情がある場合には、家庭裁判所に期間の延長を請求できます。
↓
● <4ヶ月以内> 所得税の準確定申告
・ 税務署に提出(故人が所得税申告者であった場合)
※ 死亡年の1月1日から死亡した日までの確定した所得金額及び税額を計算して、相続開始を知った日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。
↓
遺産分割協議 ・ 遺産分割協議書の作成
↓
● <10ヶ月以内> 相続税の申告
・ 税務署に申告(基礎控除額を超える方のみ申告が必要です)
【基礎控除額の計算方法】
3000万円 + (600万円 x 法定相続人の数)
遺産が、基礎控除額以下の場合には、相続税の申告は必要ありませんが、遺産が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
財産分割

相続手続きの中で、最も複雑で時間のかかるものです。
● 相続人調査
● 相続財産調査
● 遺産分割協議
(遺言書があるときは必要ない場合もあります)
特に「相続人調査」と「相続財産調査」を怠ってはいけません。
相続人調査を怠り、一部の相続人を欠いた状態で行われた遺産分割協議は無効となり、再び一から遺産分割協議をやり直さなければなりません。
また、相続財産調査を怠ると、結果的に多額の借金を背負うことにもなりかねません。特に債務の有無(抵当権の有無なども)は、徹底的に調査することが必要です。
なお、故人が誰かの保証人になっていた場合 (注2) には、その地位も相続されるので注意が必要です。
この場合、どうしても保証人になりたくなければ「相続放棄」という手続きがあります。しかし放棄をすると、家、土地、その他のプラスの財産もすべて相続することが出来なくなります。
(注2)
原則として保証債務は相続しなければなりませんが、一部例外があり、「身元保証」、「信用保証」の場合には相続する必要はありません。
ただし、どちらの場合も、具体的な債務が発生しているときには相続しなければなりませんし、契約内容によっては相続の対象となる場合もあります。
相続の方法 ~ 承認か放棄か ~
● 単純承認
被相続人(故人)の権利や義務のすべてを引き継ぎます。被相続人に財産があれば、その財産を受け継ぐことができますが、同時に債務(借金など)も受け継いでしまいます。
単純承認をすれば、どんなに債務が多くてもすべて責任を負うことになるので、十分な調査をする必要があります。
● 限定承認
相続した財産で支払える限度においてのみ、被相続人の債務を支払います。
つまり、財産から債務を差し引き、それでも財産が残っていればその財産を相続しますが、財産を超える分の債務には責任を負わなくてもよいという、相続人の安全を図る制度です。
● 相続放棄
相続の放棄とは、その相続に関して財産も債務も受け継がないことです。
多額の借金がある場合や財産を受け継ぐことを潔しとしない場合、争いに巻き込まれたくない場合などは相続放棄をしたほうが良いでしょう。
しかし相続放棄をしたとしても、相続財産の全部または一部を処分したときなどは相続放棄が認められなくなる場合もありますので注意してください。
相続方法の決定

相続人となったひとは、自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内(これを熟慮期間といいます)に、どの相続方法を選択するのか決めなければなりません。
単純承認の場合には特に手続きは必要ありませんが、限定承認と相続放棄の場合には、家庭裁判所に申し出ることが必要になります。
したがって、相続人の間だけで遺産を放棄すると約束をしても正式に相続放棄をしたことにはならず、債務がある場合には引き継ぐことになりますので注意が必要です。
また、相続の承認および放棄は、原則として撤回することができません(3ヶ月の期間内でも同様です)。期間が短いために焦ってしまいがちになりますが、しっかりと調査や話し合いをしたうえで決定をすることが重要です。
熟慮期間の伸長
相続財産の状態や相続人の関係が複雑で、3ヶ月以内に相続の方法を決めることが難しい場合には、利害関係人または検察官は家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長の申し立てをして、期間を延長してもらうことができます。
資産と負債の額がはっきりと分からず、熟慮期間内に調査することが難しいと思われる場合は、家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長を申し立て」をしましょう。そして相続財産の調査を十分に行うことにより、後になって思わぬ負債が出てくるという事態をふせぐことも可能となります。
ただし、この申し立ては熟慮期間内にしなければなりませんので注意してください。
遺産分割
相続人が複数いる場合には、各相続人に相続財産を分割しなければなりません。

この遺産の分割方法には4つの形態があります。
● 指定分割
遺言で指定された方法にしたがって遺産を分割します。
● 協議分割
相続人全員の話し合い(遺産分割協議)により遺産を分割します。
● 調停分割
相続人の間で何度話し合っても遺産分割協議がまとまらない場合などは家庭裁判所の調停を利用することになります。
● 審判分割
調停でも成立がしない場合は、自動的に家庭裁判所の審判が開始され、それにより遺産を分割します。
遺産分割協議書の作成
誰にどれだけ、どの遺産を分けるかをまとめたものを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書は、特に作成する法律上の義務はありませんが、相続人全員が話し合いに合意したという証拠として遺産分割協議書を作成することによってトラブル防止になりますし、相続財産である不動産の移転登記や銀行での預貯金の払戻手続きの際に添付書類として、この遺産分割協議書が必要になる場合があります。
後から相続人の間での言った言わないの争いの発生を未然に防ぐためにも、きちんと話し合いの内容を盛り込んだ遺産分割協議書をしっかりと残しておくことは大事なことです。
また、せっかく作成したが遺産分割協議書の内容に不備があったり、不動産の相続登記の際に必要事項が記載されていないということにならないためにも、専門家のアドバイスに基づいたしっかりとした書面を作成することが重要です。
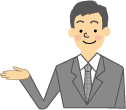
この他にも相続の手続きにはやらなくてはならないこと、知っておくべきことが多くあります。
また、人生が人それぞれ違うように相続の悩みも十人十色であり、一人ひとりに適した手続きの進め方があると思います。
当事務所では認定相続カウンセラーの行政書士が、お客様の想いをしっかりとお伺いしたうえで最適な手続きをご提案し、ご依頼者様の心の負担を少しでも軽くすることが出来るよう誠心誠意お手伝いさせていただきます。
 みなとこうべ行政書士いとう総合事務所
Minato-Kobe Gyoseishoshi Lawyer office Ito
遺言、相続、成年後見など、ご家庭の法務に関する
お困りごとを、誠心誠意サポートいたします
お気軽にご相談ください
みなとこうべ行政書士いとう総合事務所
Minato-Kobe Gyoseishoshi Lawyer office Ito
遺言、相続、成年後見など、ご家庭の法務に関する
お困りごとを、誠心誠意サポートいたします
お気軽にご相談ください