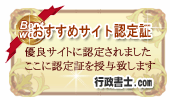遺言書
● 遺言書作成の効用 = 想いやりを形に残すことができます
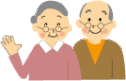
・ 財産争いを予防することができます。
・ ご家族への感謝の気持ちも書き添え、円満に財産分与できます。
・ 自身の財産を、お世話になった方、今後を託したい方などに分与できます。
「遺言書」と「遺書」の違い
遺言書を書かない、または書きたくないという人の理由のひとつに、「遺言書」を「遺書」と同じように考えているということが挙げられます。 両者は実際にはまったく違うものです。
【遺書とは】
「死ぬこと」「亡くなること」を前提に、自分の気持ちを家族や友人・関係者に書き記したたものです。
・ 主に、身の潔白、自己保身、加害者への非難、恨み、家族への想いなどを書きます。
・ 所定の書式は存在せず、自由に想いを書き連ねることができますが、法的効力はありません。
【遺言書とは】
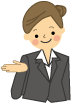
死後に自身の財産をどのように処分するかを、自分の意思により決めることができるものです。
法的効力があります。そのため、民法に規定される厳格な要件を備える必要があります。
ゆえに、遺言書でできること(遺言事項)についても厳格に定められています。
遺言でできること (遺言事項)
形式的に有効な遺言書であっても、すべての内容が法的な効力を持つものではありません。
遺言によってできることは、法的には主に次の3点に集約されます。
① 相続および財産処分に関すること・・・相続分や遺産分割方法の指定、相続人の廃除やその取消しなど。
② 身分に関すること・・・子どもの認知、未成年後見人の指定など。
③ その他・・・遺言執行者や祭祀承継者の指定、生命保険金の受取人の変更 (注1) など。
(注1) 保険の受取人の変更を遺言で出来るかどうかについて、かつては商法に規定がなく、判例・学説でも見解が分かれていました。
しかし今日においては、改正保険法44条により、保険金受取人の変更を遺言により出来ることが明記されています(同条1項)。
もっとも、保険会社に二重払いの危険があるため、契約者の死亡後に、相続人のうちの1人(または遺言執行者)が保険会社に通知しなければ、遺言による変更を保険会社に対抗できないことも明記されました(同条2項)。
以上から、遺言による保険金受取人の変更は可能であるが、相続人か遺言執行者からの通知が必要になるため、特に受取人を第三者に変更する場合には、遺言執行者を選任しておきましょう。
遺言書の種類
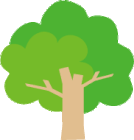
遺言には、法的に大きく分けて「普通方式」と「特別方式」によるものがあります。
このうち「特別方式」による遺言は、伝染病などにより隔離されている場合や、
船や飛行機が遭難して危難が迫っている場合など、いずれも特殊な状況下
でおこなわれるものです。
そのため、通常は「普通方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)」
により作成します。

【 自筆証書遺言 (じひつしょうしょいごん) 】
すべての内容を遺言者本人が自筆で書いた遺言です。したがって、パソコンなどで作成したり、他人に書いてもらった遺言は無効となります。
保管場所には注意が必要です。(間違って廃棄されたらそれで終わりです)
<メリット>
● 費用もほとんどかからず、手軽に作成できる
● 遺言書の存在や内容を秘密にできる
● 証人がいらない
(注2)
<デメリット>
● 要件不備によって無効になるおそれがある
●
第三者に偽造・変造されるおそれがある
●
発見されなかったり隠匿されるおそれがある
(注2)・・・ 自筆証書以外の遺言については、すべて証人が必要になります。

【 秘密証書遺言 (ひみつしょうしょいごん) 】
自筆証書遺言の場合と異なり、遺言者が必ずしも自筆しなくてよいのが特色で、遺言の内容を秘密にしながら遺言の存在を明確にできます。
自己の管理下で作成した遺言書を公証役場へ持ち込み、遺言書であることを公証人が公証するものです。
自筆証書と同じく、保管場所には注意が必要です。
<メリット>
●
遺言の内容を秘密にできる
●
パソコンでの作成や代筆も可
<デメリット>
● 要件不備によって無効になるおそれがある (注3)
●
紛失したり発見されないおそれがある
(注3)・・・ 秘密証書遺言としての要件が欠けていても、自筆証書遺言としての要件を備えていれば
有効な自筆証書遺言として認められます。

【 公正証書遺言 (こうせいしょうしょいごん) 】
公証人によって作成してもらいます。秘密証書遺言とは異なり、遺言の内容にも公証人が関与し、また作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失、偽造、変造のおそれがありません。
<メリット>
● 無効になるおそれがほとんどない
● 偽造・紛失・隠匿のおそれがない
● 家庭裁判所による検認が不要 (注4)
<デメリット>
●
ある程度の手間、時間がかかる
●
遺言の存在や内容を秘密にできない
●
証人に遺言の内容を知られる
(注4)・・・ 検認とは遺言書の偽造や変造を防ぎ、遺言の内容を明確にするために行われる手続きで,
遺言を発見し又は保管していた者は、遅滞なく家庭裁判所に検認の請求をしなければならない。
公正証書遺言以外の遺言については、すべて家庭裁判所による検認が必要になります。
※ 封印のある遺言書を検認前に開封した場合は、5万円以下の過料に処せられます。
まとめ

費用をあまりかけずに手軽に作りたい方には自筆証書遺言がおすすめ
ですが、一般的には安全で確実な公正証書遺言がすすめられています。
しかし、一概に自筆証書遺言のほうが劣っているとは言えません。
要は、安全・確実性、作成の簡便性、費用面、検認の要否などのうち
何を重視するかです。
遺言内容の複雑さなども勘案し、自分にふさわしい方式を選ばれると良いと思います。
当事務所では、遺言書・エンディングノート・尊厳死宣言書に関するあらゆるご相談から作成、執行を通じて、しっかりとご依頼者様の想いを残された方に届けると共に、争いを未然に防ぎ、円満に解決することが出来るよう、誠心誠意をもってサポートしております。
 みなとこうべ行政書士いとう総合事務所
Minato-Kobe Gyoseishoshi Lawyer office Ito
遺言、相続、成年後見など、ご家庭の法務に関する
お困りごとを、誠心誠意サポートいたします
お気軽にご相談ください
みなとこうべ行政書士いとう総合事務所
Minato-Kobe Gyoseishoshi Lawyer office Ito
遺言、相続、成年後見など、ご家庭の法務に関する
お困りごとを、誠心誠意サポートいたします
お気軽にご相談ください