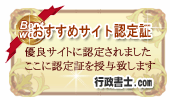相続 ・ 遺言

「まさかうちの親族に限ってもめるはずがない」と思っている方が多い
かもしれませんが、財産をめぐって親族の関係が悪化したりすることは
少なくありません。
特に、家族関係が複雑であったり、相続人の数が多い場合や自宅以外
にこれといった財産がない場合などは、さらに争いになる可能性が高く
なります。
親族の間で争いごとが起こらないよう、事前に配慮しておくことが必要かもしれません。
相続
相続というのは、被相続人(死亡した人)の権利や義務を相続人が受け継ぐことです。
※相続はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含むすべての財産を受け継ぐので注意が必要です。
(相続財産の調査の結果、マイナスの財産が多いときは相続放棄なども考慮する必要があります)
相続人が何人かいるときには、相続財産(遺産)はそれぞれの相続人の共有(みんなのもの)になっているので、その遺産を各相続人のものにするために分割します。
【遺産の分割】
遺産は遺言書があればその通りに分割し、遺言書がなければ法定相続分に従うか、又は相続人全員でどのように分割するかを協議します。
相続人の間で遺産をどのように分割するかを決めたら、あとで問題が起こらないように書面(遺産分割協議書)にしておくことが望ましいです。

突然の相続手続き、いったい
何から始めればいいの?
●公共料金・電話などの名義変更
●年金・保険関係の手続き
●相続人及び相続財産の調査・確定
●預貯金・株式・自動車などの相続手続き
●不動産の名義変更
など
各ご家庭によって必要な手続きは、まだまだたくさんあります。
また、相続放棄をする場合や相続税の申告が必要な場合などは、期限が定められているため、順序よく手続きを進めていく必要があります。
遺言
遺言と聞くと縁起でもない、財産のある人だけが書くものだなんて連想される方が多いかも知れません。
しかし、ご家族へ感謝の気持ちを伝えると共に、相続を円満に解決できる方法は、実は遺言しかありません。
【遺言の意義】
“遺言”とは、元気で生きていくことを前提に、もし自分に万が一のことがあった場合に大切な人たちが生活に困らないように、また無用な争いに巻き込まれることの無いように備えておくための「愛情のしるし」であると思います。
財産争い予防のために、今までの感謝の気持ちや伝えることのできなかった想いと共に、あなたの思いやりとしてしっかりと形にのこしておきましょう。
※遺言の形式は法律によって厳格に定められており、この定める形式に従わない遺言は無効となります。

遺言書なんて・・・
ウチには必要ないよね?

「ウチは財産が少ないから・・・」
「ウチはみんな仲が良いから・・・」
という理由のみでは、必ずしも相続争いを回避できるとは限りません。
遺言書を作成することで無駄な相続争いを防ぐことができ、ご家族への負担を軽減することができます。
 みなとこうべ行政書士いとう総合事務所
Minato-Kobe Gyoseishoshi Lawyer office Ito
遺言、相続、成年後見など、ご家庭の法務に関する
お困りごとを、誠心誠意サポートいたします
お気軽にご相談ください
みなとこうべ行政書士いとう総合事務所
Minato-Kobe Gyoseishoshi Lawyer office Ito
遺言、相続、成年後見など、ご家庭の法務に関する
お困りごとを、誠心誠意サポートいたします
お気軽にご相談ください